「両手を右肩におくでしょ。こうして、ちょっとあごを持ち上げるわけ。そうするとほら、もう足笛!って感じするでしょ?これがやりたいのよ、わたし」
青子は熱烈に語る。ひとつ配役が決定しそうだな、と思いながら阿枝はバーについた。別に自由なのだが、なんとなく全員いつも同じ場所のバーをとる。阿枝は青子と子信の間。
子信の前は祭で、ふたりは左足をバーにおいたまま何か話をしていた。王子には誰がなるかをあてているらしい。祭は青子と阿枝を見ると、彼女たちにまで話題を吹っかけてきた。
「さおこちゃん、アエダ、誰が王子になると思う?森羅か俊二か、でも今回のガラだし、つづくでも綺羅人でもありえるよね」
「それはどうでもいいのよ」
祭が言い終える前に、青子はあっさりと切り捨てた。
「は?」
「問題は足笛よ。足笛なの。まつりちゃん、わたし足笛がやりたいんだけど、どう思う?」
「え」
「まつりちゃんなら分かると思うの、わたし足笛につけると思う?」
青子は真面目だったが、祭はひいていた。
「そんなの、彩子さんに聞きなよ」
「あら、そんな緊張することできないわ。なんかホラ、ももえちゃんなんかちょっと『足笛ですカッコはあとカッコ閉ジ』って感じじゃない?あああ、わたしはできないかなあ」
「さおこちゃん、足笛って女性ダンサーふたりでんのよ」
「でもアエダちゃんなんかも『足笛』ってかんじだし。不安だわあ」
この会話の間、子信は黙々とバースプリッツを繰り返していた。
「ねえ、立候補制にしてくれないかしら。そのなかでオーディションするの、どう?」
「だから彩子さんに言ってよ」
「もお、頼りにならないんだから」
ばしり。
祭がガクリと肩を落とした。背中が子信の左の甲に当たる。
「さおこちゃ……あんたが一番年上なんだよ」
「でもまつりちゃんが一番上手なのよ」
左足をバーにおいて右足をプリエにすると、阿枝はちょうどバースプリッツを右足に変えた子信と目が合った。
子信はにこりともせずに、筋を伸ばしながら
「アエダは何を踊りたい」
と訊いた。
子信はおそらく、祭の次に上手い。そして祭よりずっと真面目だ。祭がおちゃらけているのと反対に、日々真剣にバレエをしている。でもそれは、バレエが好きで好きでたまらないからというよりも、誰よりもうまくなりたいという目的で踊っているように見えた。それは同じなようで微妙に違う。祭と子信は仲がいいが、子信はいつか祭を追い抜こうと必死なのだ。子信はいつも切羽詰っている。
「どれでも……」
「金平糖でも?」
「そんなの、選択肢から外してる」
子信はちらりと阿枝を見た。
「ソロだから?そんなこといってもみんな似たようなものだよ。アラビアだってふたりで男女ペアだし。中国と足笛なら女はふたりだけど」
「わたし、中国の踊りのあんな速い回転はできないよ」
「ああッ!」
青子が悲鳴を上げた。
「アエダちゃん裏切ったわね。足笛やりたいのね!」
「そんなこと言ってない」
「不純な動機ではダメよ。どうしても足笛が踊りたい子が足笛を踊るべきだわ。ねえまつりちゃん」
「だから知らないってば」
「わたし、断固、抗議するわ」
「どうぞ」
そのとき、青子にいい加減な返事を返しながら、祭がフェッテの練習を始めた。
トゥ・シューズは履いていなくて、爪先に何も入っていないバレエシューズで。でも、ポアントで立って回ったところできっと何も変わらずに完璧な回転が出来るだろうと思わせる、寸分のずれもないフェッテ。
フェッテをやめると、その足であくびをするように四回転をし、のびをする。
「あああ、彩子さん遅いねえ」
ごく自然な動作で。
子信が無言でバーを離れて、二、三歩歩いて立ち止まり、回転の姿勢を作った。右まわりのフェッテ、顔を残して、勢いでなくバランスを保ちながら。
十回ほどまわり終わると、下りた足で四回転。最後少しぐらついた。
「のぶ、やっぱり左足だと軸が少しずれてくるね」
バーに寄りかかってみていた祭が口を開いた。
「六回めくらいから。ポアントだったら完璧にぐらついているよ」
「……七回めだよ」
ぼそっと言う子信。
祭がにっと笑った。
「ちょっとちょっと、まつりにのぶ。それにアエダにさおこちゃん」
大声に、我に返って振り返ると、百重と赤李が手招きしていた。稽古場のドアの小さな窓にたかっていて、まわりに森羅たち男子が全員べたっと貼りついている。
「なんかあっちに彩子さんがいるの」
「ナマケモノと話しているんだけど」
祭がエッと声をあげて駆けていった。阿枝と青子も追いかける。
ナマケモノというのは生徒たちが呼んでいるあだ名で、本名を湯田悦二朗。生徒はよく知らないが、彩子さんよりずっと偉い、この学校の核にいるオジサンだときいていた。
「えー、なんか言い争ってるみたいじゃん」
男子らをおしのけて小窓を占領しながら、祭がつぶやいた。
「言い争いっていうより、彩子さんが抗議しているって感じじゃないか。何かあったのかな」
「やめてよ森くん。やだなあ、なにかあるとしたら、わたしたちのことなんだから」
百重が不安気な声をだす。俊二が飽きたらしく、バーへ戻っていった。
「きっと誰かが退学になるんだ。ぼくかもしれない、最近レッスンつづけて二回も休んだから……」
「満、あんたそのネガティヴさをまずどうにかしな」
祭がビシリと言う。満がきっと振り返った。
「ぼくはまつりちゃんと違ってうまくないから、自信が持てないんだよ」
「そんなこと自慢するなよ」
森羅が苦笑いする。
彩子が何か激しい口調になった。ナマケモノがたじたじとなる。
「あっ、来るよ」
綺羅人が叫ぶ。
小窓からみんながわっと離れて、ダッシュでバーについた。
最後、赤李がバーにたどり着いた瞬間、勢いよくドアが開く。
「さあみんなちゃんとバーについて!レッスンを始めますよ!」
「彩子さん」
うしろからナマケモノが渋い声を上げる。
「何のためにわたしが来たと思っているんですか。レッスンのまえに生徒を集めてくださいよ」
「実力も見ずに何言ってるんですか。まず踊りを見てください」
「だけどねえ、わたしはそんなに時間がないんだよ」
あの彩子さんに言い返せるとはなかなかすごい。ナマケモノ。
「なんなんだろうね」
青子が阿枝に耳打ちした。
「ガラ公演のことよねえ」
俊二がつまらなそうにひゅーっと口笛を吹く。それは祭のそれと重なって、なかなか綺麗にハモッた。
「森羅くん、俊二くん!」
それからぶつぶつオトナは二人で何かやりとりをして、のち彩子のとがった声が響いた。
「ちょっとここへ来て並びなさい」
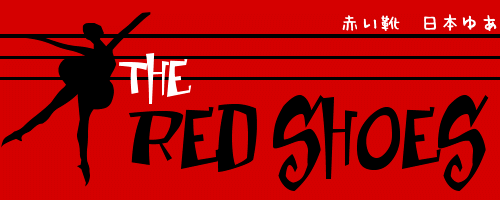
01:誰が為に花は咲く (3)
赤い靴

top
------------------------
1章(1)(2)(3)(4)
------------------------
2章(1)(2)(3)(4)
------------------------
3章(1)(2)(3)(4)
------------------------
4章(1)(2)(3)(4)
------------------------
5章(1)(2)(3)(4)
------------------------
とりあえず5まで……